大学入試や各種資格試験には「テクニック」があります。これらに共通しているのは過去問の反復や習慣化した生活リズムなどが挙げられます。しかし今回は私の経験談として記事を書いてみました。
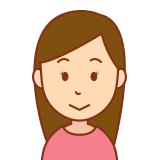
学生時代までは、期末テストの時期になると一夜漬けしたりして何とか乗り切っていたわ。

私も同じくです。睡眠時間を犠牲にし、気合で徹夜して必死に暗記。なんとか乗り切りましたが、仕事しながらの勉強だとそのやり方には限界を感じました。
FP試験、覚えることが多すぎる…?
「FP試験って、覚えることが多すぎて無理…」
学習を始める前、そんな声を耳にしましたが、過去の”成功体験”でそれを無視。いざテキストを購入して問題を解いてみると、税率、控除額、制度の名称、適用条件…。
確かに情報量は膨大で、最初は“暗記ゲー”でした。
私がFP3級試験を受験したのは39歳のときでした。
40歳目前の年齢は、世間的には「一人前」と言われる世代。
年金や医療保険、自動車保険、持ち家や賃貸など、ある程度の制度や仕組みには触れてきました。
でも、試験勉強を通して改めて気づいたのは、
「知っているつもり」だった制度の背景や意味を、実は深く理解していなかったということ。
この学び直しは、単なる資格取得以上の価値がありました。
初回の試験で学科は合格。実技は不合格。学科の試験は正直なところ気合(暗記)に頼るところが大きく、実技に関しての振り返りでは、「暗記だけでは無理だ」と思いました。それから実技の過去問を繰り返し反復して何とかギリギリで合格することができました。しかし、ちゃんと論点を理解して合格をしたというよりは、「逃げ切り合格」でした。
暗記では太刀打ちできないFP2級
FP3級のときは、ほぼ「暗記と気合」で乗り切りました。
言葉の意味もよくわからないまま、「こう出題されたらこのように解く」と、過去問のパターンを頼りに“力技”で解いていたのです。
しかし、FP2級に挑戦したとき、状況は一変。
難易度が上がり、単なる暗記では通用しなくなりました。
そこで私は、FP試験で出題される6分野の中で、特に気になった専門用語を調べるようになりました。
制度の“言葉”から本質を読み解く
たとえば:
- 被保険者 → 保険のサービスを“被る”者。つまり、保険のサービスを受ける人
- 悪意 → 知っている者
- 瑕疵 → 欠陥
- 過失 → 落ち度
- 養老保険 → 老いを“養う”保険。だから毎月支払う保険料が高い
- ○○税(所得税・住民税など) → 国民(市民)からしっかりと税を徴収するための制度。制度設計には徴収の公平性と確実性が反映されている
こうした言葉の意味を理解することで、制度の“背景”や“趣旨”が見えてきます。
それまで「選択肢のどれが正しいか」だけを見ていた学習が、
「なぜこの制度にはこの条件があるのか?」という視点に変わったのです。 保険分野なら保険会社のHP、金融分野なら証券会社のサイトなど、専門機関の用語解説ページを活用することで、制度の本質に近づけました。
今では、分からない用語があればAIに聞くのが一番早いと感じています。
暗記 vs 理解、どう見極める?
FP試験3~2級の攻略では、「覚えるべきこと」と「理解すべきこと」を仕分けることが重要です。
| 項目 | 暗記すべき | 理解すべき | 解説 |
| 税率・控除額 | ○ | 数字は変動するため、試験対策として暗記が必要 | |
| 各諸制度適用要件 | ○ | ○ | 条件は覚えるだけでなく、なぜその条件なのかを理解すると定着しやすい |
| 制度の趣旨 | ○ | 制度の背景や目的は、選択肢の正誤判断に役立つ | |
| 法改正の背景 | ○ | 改正の理由を知ることで、制度の流れがつかめる | |
| 用語定義 | ○ | 基本用語は覚えるだけでOK。深掘りは不要な場合も多い |
このように、「数字や定義」は暗記、「制度の仕組みや理由」は理解という視点で学習を進めると、
効率よく知識が定着し、応用力も高まります。
学習法:効率よく学ぶための3ステップ
- テキストを色分けして読む
→ 暗記すべき部分(数字・定義)と、理解すべき部分(制度の趣旨)をマーカーで分ける - 過去問を“理由づけ”して解く
→ 正解・不正解の選択肢に対して「なぜそうなるのか?」を自分の言葉で説明してみる - 専門用語は“背景”から調べる
→ 保険会社や証券会社のサイト、AIなどを活用して、制度の目的や仕組みを理解する
学び直しは“納得”から始まる
FP試験は、すべてを覚える必要はありません。
むしろ、「覚えるべきこと」と「理解すべきこと」を見極める力こそが、合格への近道です。
制度の“要件”と“理由”をセットで理解することで、
知識が定着し、応用力も身につきます。
そして何より、39歳での挑戦を通して感じたのは、
制度を“納得”することで、学びが自分の人生に根づいていくということ。
FP試験は、単なる資格ではなく、“自分ごと化”できる学びの入り口なのです。
さらに、FP試験は絶対評価方式の試験であり、
全体の6割の点数を取れば合格できます。
だからこそ、すべてを完璧に覚える必要はありません。
私自身は、練習では過去問の8割正解を目指し、
間違えた問題は必ず解き直すようにしていました。
そして、2~3日後に再度その問題を解いてみる。
この“間隔を空けた復習”を繰り返すことで、知識が定着し、得点力が着実に伸びていきました。
「暗記と理解のバランス」
それこそが、FP技能士試験を乗り越えるための最も現実的で、効果的な学び方だと私は実感しています。
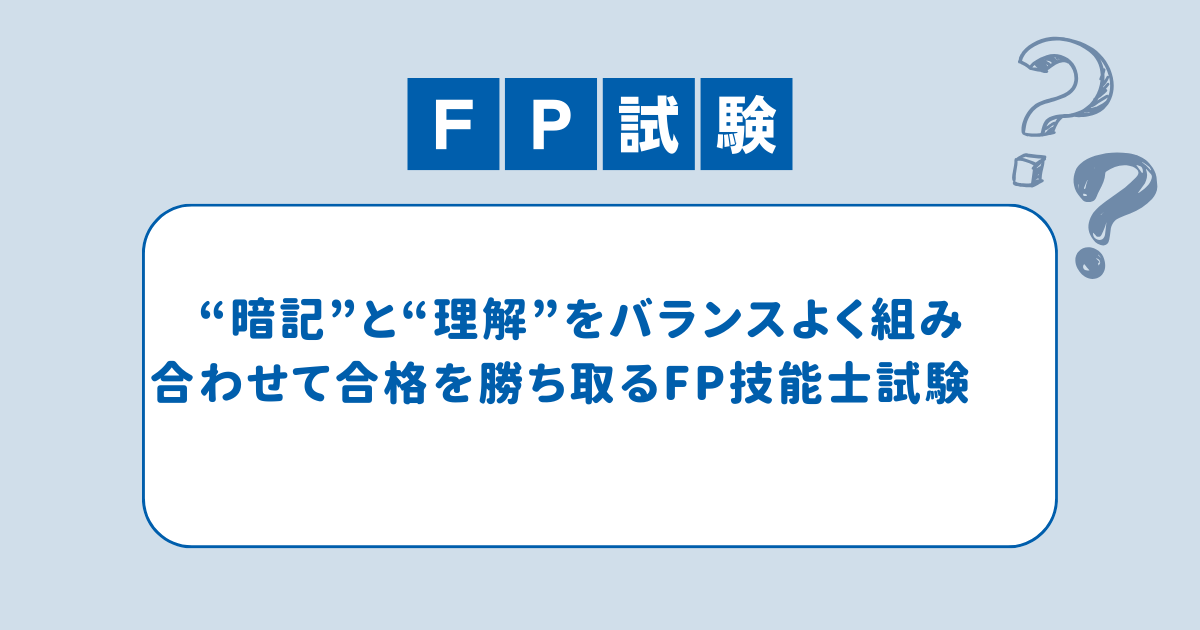


コメント